珍しく執筆意欲に溢れてるんで連投。とはいえガッツリしたもん読む余裕はないんで、読み返す必要のないやつをば。浅田次郎『勝負の極意』幻冬社アウトロー文庫(1997)。多分二度目の浅田次郎。『鉄道員』ヒット前に口に糊する為に書き散らかした競馬指南書と余ったページに処女講演を文章化。明らかにやっつけ企画の匂いがプンプンするのに、しっかり読ませるんだからたいしたもんです。『じゃじゃ馬グルーミン★UP』位でしか競馬をしらない私ですが、負けを覚悟でウィンズへと走りたくなりました。明日でも行ってみようかしらん。以下ネタバレ注意。

- 作者: 浅田次郎
- 出版社/メーカー: 幻冬舎
- 発売日: 1997/04/01
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 3回
- この商品を含むブログ (13件) を見る
私はこうして作家になった
まず処女講演から。自衛隊→サルベージ屋*1→ブティック経営→小説家と妙な職歴を持つ浅田氏ですが、小説家になるというのは当初からの目標だったらしく、各時期にどんな苦労をして修行を積んだか、というのがメインテーマです。幾度の新人賞落選にもめげず40の声を聞いてからデビューを果たした氏の執念は凄まじいですが、一般的には文才なんてのは天賦のものなんで、何年努力しようが無理なもんは無理みたいです。バブル期の名残でフリーライターも溢れてるみたいですし、まだ暫くペン一つで世を渡ろうって人には氷河期が続きそうです。閑話休題。氏は当時ピカレスク作家から本格派への移行期にあったのですが、この講演でも自分が今までユーモア悪漢小説*2のは不本意で、自分は本当は本格的純文学なのだと強調しています。『極道放浪記』で氏を知ってファンになった身としては非常に残念です。「文壇」の「純文学」偏重主義は大概にして欲しいものです。清く正しく俗物的なエンターテイメントこそが「小」説のあるべき姿だと思います。最後に氏の勧める文章修行法、「名作文学をともかく筆写すること」だそうです。アナクロな浅田氏らしく微笑ましいのですが、効果は保証します。本気で作家を目指す若人は試してみてください。華麗な文章が身につくはずですただし、これをやっても構成力は身につかないのは浅田氏が身をもって実践*3してますので、そこはシナリオライター養成講座にでも通ってください。
私は競馬で飯を食ってきた
続いて競馬指南書。戦術論ではなく戦略論で、競馬における経済観念の重要さを説いています。JRAの25%*4という法外なテラ銭*5に負けず、終始決算をプラスに持ち込む為には、遊びで買うんじゃなく真剣にやらねばダメだというのが結論でしょうか。昔から飲む・打つ・買うは男の甲斐性などと申しますが、さもありなん、と思わせます。博才の欠片もない身としては大変憧れます。「偶然すなわち神と闘う者は、常に神秘的威厳に満ちている。賭博者もまたこの例に洩れない」(by芥川龍之介)こんな文章で始まる競馬指南書が何処にあるでしょう。スポーツの皮をかぶる現在の競馬を邪道と切り捨て、競馬場を女子供の入れぬ鉄火場と位置づける氏の感覚は時代遅れながらも、いやだからこそ、鮮烈な感動を残します。もちろん実利的実践的な解説も多々あるのですが、それでも十分過ぎるくらい「ブンガク」に成り得てるのは、氏の底知れぬ才能を感じさせます。
まとめ
結論。博打は打つものじゃなく開くもの。なので今後の対策。業務連絡。後輩諸君へ。次回からは場所代いただきます。


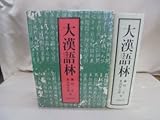

![機動戦士Zガンダム Part I ― メモリアルボックス版 [DVD] 機動戦士Zガンダム Part I ― メモリアルボックス版 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41SHNC1FW5L._SL160_.jpg)


![舞-HiME 1 [DVD] 舞-HiME 1 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51TQjNT1N4L._SL160_.jpg)

